更新日:2019年10月1日
ここから本文です。
クローズアップ
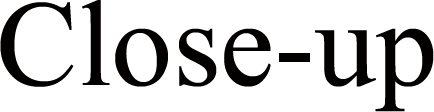
Organiccity"AIRA"

いつも見ている夜空を、ずっと見ていたい星空に――。
スターランドAIRA
それぞれの胸に輝く星に込められた想い
空気が澄んだ北山の空
子ども連れの家族を中心に、友人同士やカップルなどの若者のほか、シニア世代の方々も訪れる「スターランドAIRA」。実はプラネタリウムと大型望遠鏡を有する県内唯一の公開型天文台です。また、施設のある北山は夜間照明などの不要な光の影響が少なく、平地より気温が低いことで観測の妨げになる水蒸気が大気中に少ないため、天体観測に適した場所です。そのため、天の川や望遠鏡で覗く天体をよりはっきり見ることができます。
星も宇宙も身近なもの
旧町時代に、南北に長い地形の旧姶良町では南部に人口が集中し、北部は過疎化が進んでいました。そこで、閉校していた北山中学校を平成3年に北山野外研修センターとして再生。小中学生が豊かな自然環境の中で宿泊学習や野外活動を体験できる場を開設しました。そして「宿泊をしながら星空観察ができる」と相乗効果を期待し、平成5年7月に建設されたのが「スターランドAIRA」でした。星空を通して宇宙を身近に感じ、自分たちの住む地球を顧みる機会をつくることをめざしています。現在、市内の小学校4年生の「星と星座」の授業や小中学生を対象とした集団宿泊学習「AIRAふるさと学寮」での天文教室などにも利用されています。

思い出の星空を求めて
「父の転勤で徳之島に住んでいたころの星空が忘れられない」と少年時代から天体に興味を持ち、中学生のころに天体写真集を制作したと話すスターランドAIRAの上田聰館長。千葉県で理科の教職に就き、独自で天体観測を続けながら、その経験を子どもたちに伝えています。帰省後は、鹿児島県立博物館や科学館に勤務し、重
富中学校校長を経て、平成26年に同館の館長に就任。星の大きさや距離を身近なもので例えるなど、工夫した講義や展示物に心がけています。今も子どもの頃に見た星空の感動を追い求め、国内外で観測を続ける上田館長。「星を通して自然や歴史の楽しさ、大切さ を伝えたい」と話しました。
初代館長は「百武彗星」の百武さん
スターランドAIRA初代館長として就任したのは、二つの彗星(百武彗星)を発見したアマチュア天文家の百武裕司さんです。百武さんは、平成6年に福岡から鹿児島に移住。上田館長とは知人の紹介もあり、星を通してすぐに打ち解け、心腹の友でした。「宇宙にかける情熱がすごい人でした」と上田館長。二人で各地に足を運び、天体観測をしたこともあったそうです。その後、百武彗星を発見し、世界に名を馳せた平成8年に館長として就任。自身の経験を織り交ぜた星の話は楽しくユニークで聞く者を魅了しましたが、平成14年に急逝されました。上田館長は「百武さんの宇宙への想いを広く伝えていきたい」と話します。館内には百武さんの活躍の軌跡が展示され、その意思は現在も職員に受け継がれています。
北山ならではの演出地域に光るスタードーム
地域資源に視線を向けた新たな取り組み
昨年12月に北山校区コミュニティ協議会が北山野外研修センターで「師走の祭典in北山」を初開催しました。そば打ちやミニ門松づくり体験などが催され、夜の部ではクリスマスツリーやスタードームを地元の孟宗竹で製作。参加者は、星空に負けない幻想的な景色を楽しみました。スターランドAIRAも参加し、天体観測の体験教室を実施。来場者は望遠鏡を覗き、普段見ることのない星の姿に感動しました。
「北山の星空は郷土の自慢のひとつ」と話す同協議会の内甑達也会長。住民の友人や孫が北山を訪れたときに、その夜空の美しさに感動し、星空見たさに遊びに来る人もいるそうです。内甑会長は「夜に立ち寄れるスターランドAIRAがあることでイベントの幅が広がる」と同館と地域とが手を取り合う地域づくりを考えています。
「地域資源を見直し、校区に住む人が楽しめる活動をする。それが北山に人を集めることにつながる」と話し、今後も北山伝承館や県民の森などを含め、校区内の施設と連携した地域づくりに取り組みます。

物語の旅へ誘う星空のメロディー
プラネタリウム番組のBGMにも注目
スターランドAIRAでは、本格的なプラネタリウムを鑑賞できます。番組を季節ごとに製作し、流れるBGMは物語を盛り上げる大切な要素になります。そのBGMを作曲し、提供しているのが当時小学生だった鶴窪晏菜さん。きっかけは、5年生のときに通っている音楽教室の作曲コンサートに向けて、「星」をテーマにした曲づくりに挑戦したことでした。星や星座が好きで訪れたことがあったスターランドAIRAに足を運び、イメージを膨らませるために星空観測やプラネタリウムを鑑賞。その体験をひとつひとつ譜面に表現しました。その後、音楽教室の先生の指導も受けながら「星の街」という曲が完成。後日、曲を聞いた同館は、四季それぞれの星空を紹介するプラネタリウムの雰囲気に合うと春の番組に取り入れました。そして、ほかの季節の作曲も依頼。夏の「天の川」、秋の「星月夜」、冬の「きらめく星のかなたに」を作曲し、四季折々の神秘的な星空をイメージした4曲がプラネタリウムを盛り上げています。完成した年には、季節のBGMを広く知ってもらおうとクリスマスコンサートも開催されました。「この経験が曲や音をイメージする力につながっています」と現在は吹奏楽部に所属する鶴窪さん。「星たちの表情をいろいろな音色で表現しました。物語といっしょに楽しんでほしい」と曲には星への想いが込められています。

